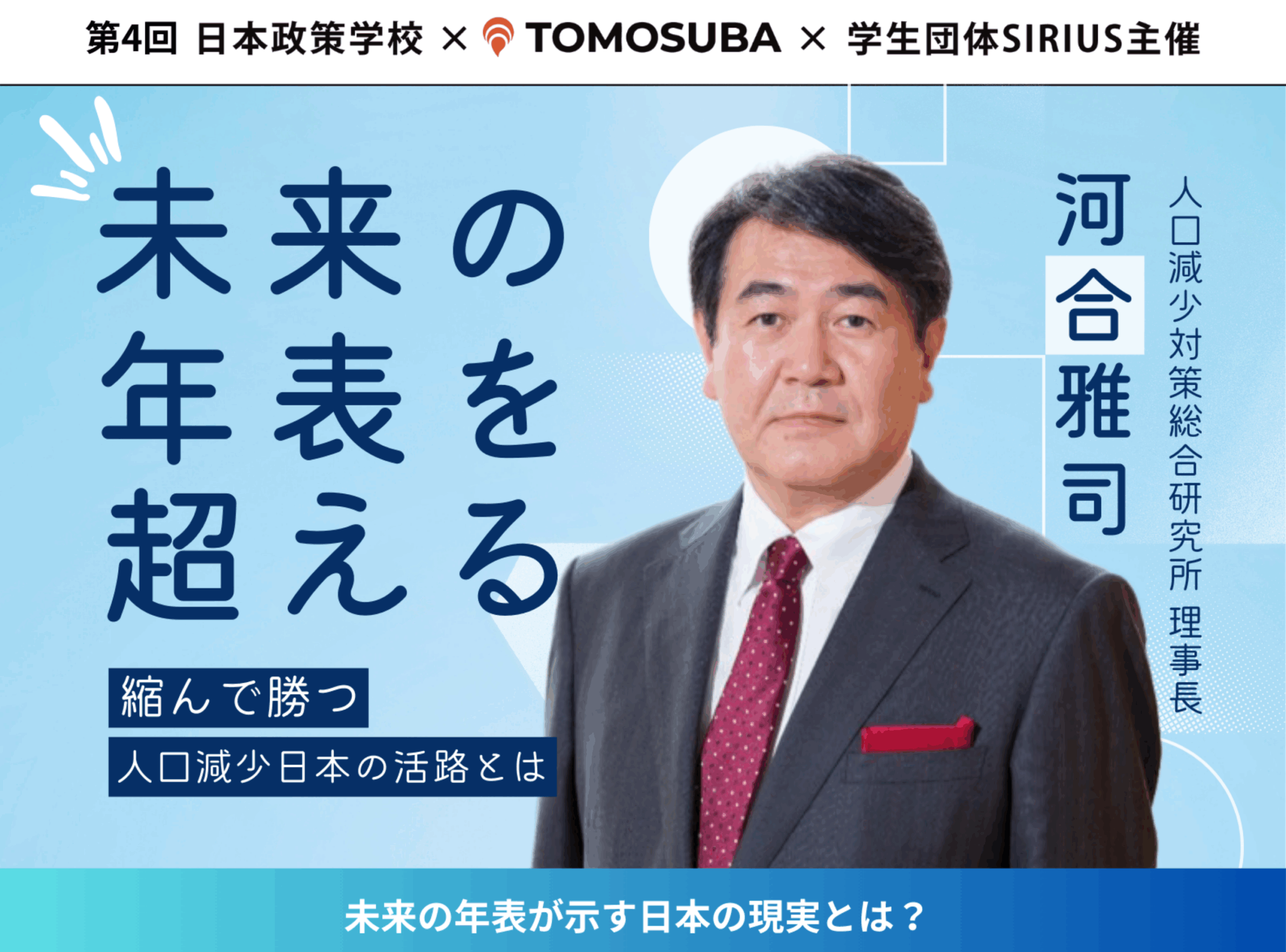◆ イベント概要
2025年8月20日、日本政策学校とTOMOSUBAの共催により、特別イベント「未来の年表を超える〜縮んで勝つ:人口減少日本の活路とは〜」を開催しました。
講師には、ベストセラー『未来の年表』シリーズで知られる、人口減少対策総合研究所 理事長・河合雅司氏をお招きし、未来の日本が直面する課題とその活路について、学生たちと共に深く語り合いました。
今回のイベントは、若者たちに日本の未来に対する関心を高めてもらい、政治や経済を「自分ごと」として捉えてもらうことを目的に実施されました。
◆ イベント開催の目的

本イベントは、政治や社会課題に対する若者の関心を高め、「政治を自分ごととして捉える」きっかけをつくることを目的に開催されました。
講演やディスカッションを通じて、人口減少という国家的テーマに対して「自分に何ができるのか」を真剣に考える学生たちの姿が印象的でした。
私たちTOMOSUBAでは、こうした社会課題に関心のある学生が多数集まっています。
企業様で「社会テーマに関心のある学生と対話したい」「次世代と社会課題を考える場を持ちたい」といったご希望がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!
※以下はイベント内容の一部を要約したものです。
◆ 河合雅司氏 講演レポート
「未来の年表」で描かれる日本の姿
河合先生は冒頭、「人口減少は静かに進行する“有事”であり、私たちが直視すべき現実です」と語りかけました。
すでに日本では毎年約100万人ずつ人口が減っており、2100年には4700万人、2300年には2000人まで減少するという衝撃の試算があるといいます。
少子高齢化・死亡数増加・地方の崩壊
・出生数は年々5〜6%ずつ減少しており、2040年には全国でわずか25万人に。
・一方、死亡者数は予測を上回るスピードで増加。2024年時点ですでに160万人を超えています。
・人口の自然減は全国で90万人を超え、「45年後には日本の人口は半分に」という試算も現実味を帯びています。
「縮んで勝つ」ための処方箋
河合氏は、これからの社会では「戦略的縮小」が必要だと訴えます。
- 高付加価値型の産業への転換(例:ポルシェモデル)
- 地域の集約とネットワーク化(「コンパクト+ネットワーク」構想)
- 外国人受け入れの社会設計と多文化共生の準備
- 高齢者・女性・外国人の労働力活用には限界がある中で、生産性の抜本改革が不可欠
社会構造全体を見直し、「価値あるものを、少ない人数で、しっかり稼ぐ国」への転換が求められていると語りました。
学生の反応
講演を聴いた学生たちは、「未来の日本の姿がよりリアルに感じられた」「自分たちが担う役割の重みを感じた」といった声を寄せ、人口減少を“自分ごと”として考える機会になった様子でした。
◆ 質疑応答
※以下は、イベント内の質疑応答の一部をわかりやすく要約したものです。実際の発言を要所ごとに編集・整理しています。

参加者A
Q1「戦略的縮小」や「高付加価値化」について非常に示唆深い講義でした。そこで以下2点を伺います
- “ちゃんとしたサービスに正当な価格を”という価値観は浸透するでしょうか? また現行の「新しい資本主義」や成長促進の政策についてどう評価されていますか?
- 「コンパクト・プラス・ネットワーク」という構想は有効だと思いますが、民間には限界もあり、政策実行が“切り捨て”と誤解される恐れも。先生の考える実行可能な仕組みとは?

河合先生
高付加価値化の方向性は間違っていませんが、それを民間投資で実現すべきです。自治体が“残ること”を目的化しては議論がぶれます。大事なのは「何人が住んでいるか」よりも「どんな未来を描けるか」。
また、今は空間も時間も越えて人がつながる時代です。従来の“地域に縛られる”発想ではなく、必要に応じて移動し創造するスタイルを目指すべきです。

参加者B
Q2「軸となる産業を地方でどう育てるか?」
地方出身者として、人口奪い合いの現実や財源の課題を感じます。特産品や観光業だけでは持続可能性に不安があります。自治体単独での産業育成には限界があるのでは?

河合先生
住民税の増税などは現実的ではありません。むしろ、その土地にビジネス上の優位性があるかを起点に、外から人と投資を引き込む方が効果的です。軸は行政でなく、事業家が創るべきです。

参加者C
Q3「大胆な少子化対策はなぜ実行されないのか?」
子ども3人で1000万円給付など、インパクトのある政策が必要では?

河合先生
その通り。ロシアでは家を無償で提供するなどの政策で出生数を伸ばした例があります。日本でも議論の場にのせること自体に意味があります。

参加者D
Q4「人口減少時代に、事業会社としてどうあるべきか?」
映画関連企業で働いています。売上以外に企業価値を上げるために必要な視点とは?

河合先生
重要なのは「縮小にどう対応するか」。多事業展開から選択集中型へ、少人数で高付加価値を生む体制に移行すべきです。それが従業員の生産性・賃金向上にも繋がります。
本日の質疑応答を通じて、人口減少社会における私たち一人ひとりの在り方や、地域の未来に対する多様な視点が浮き彫りになりました。参加者の皆さまからの率直で鋭いご質問により、議論はさらに深まり、多くの示唆を得ることができたかと思います。河合先生のお話とあわせて、これからの行動や思考のヒントとしてぜひお持ち帰りください。
◆ 最後に|企業様へのご案内
TOMOSUBAでは、今回のように社会課題や未来の働き方に関心のある学生と企業・専門家をつなぐイベントを企画・運営しています。
「若手と社会課題について対話してみたい」
「Z世代のリアルな声を聞きたい」
「インターンや採用の前段階で関係構築したい」
そんな企業様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。次のイベントを一緒に企画しましょう!